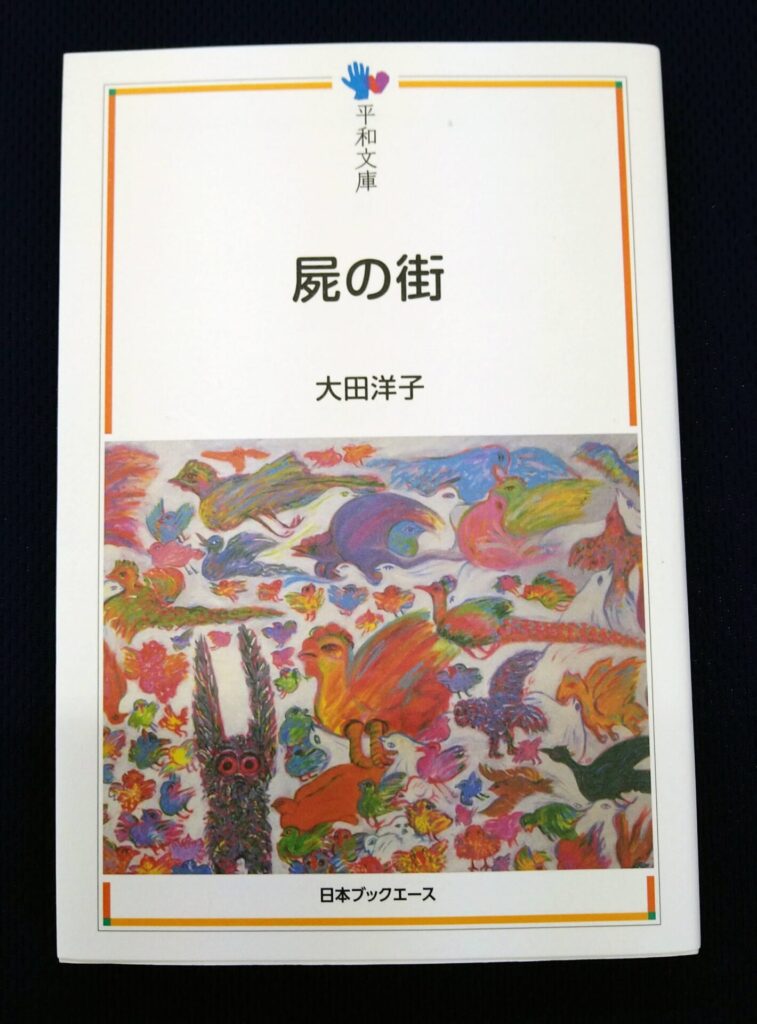
昭和20年8月6日、広島市白島九軒町で原爆を被災した作家・大田洋子が、三ヶ月も経ずに脱稿した『屍の街』。作品にでてくる地の“いま”を歩きます。後篇では、横川、廿日市、玖島を巡ります。
目次
白島・逓信病院
土手からの眺め
土手から見渡せる平地の町々、九軒町も中町も北町も東町も、遠い町々まで眼のとどくところまではみんないちめん瓦礫の原になり、ところどころに火がとろりとろりと燃えのこっているのが見えた。(中略)あらゆる電線は破れた蜘蛛の巣のようにひっからまって、めちゃくちゃに垂れさがり、瓦礫の道にとどいてそこいらを這いまわっている。それに電気でも通っているように私たちは恐る恐る、ぶら下っている電線にふれないように歩くけれど、一本もふみつけないで行くことは出来なかった。(94-95頁)
いまは住宅やビルが立ち並ぶ「土手」からの風景。遠くまで「瓦礫の原」と化した。

逓信病院
逓信病院は河原から六、七丁、同じ白島のうちの逓信局の傍にあった。その途中の電車道へ出て行く通りは商店街だった。どこがどの店だったかわからない。ただ錆びついたような色に焼けて細く歪み、骨のようになったおびただしい自転車がそこいら中にころがっているのだった。道はまだところどころ火焔を吹いていた。(95頁)
逓信病院に向かう当時の「商店街」と思われる道。

電車道へ出た。レールはくねり曲って、横へはみ出ていた。一台の電車が茶褐色の亡骸となって、流れ出したレールのうえにとりのこされていた。(95頁)
・・・私たちは電車の通りから右へまがった。するとそこには右にも左にも、道のまん中にも死体がころがっていた。死体はみんな病院の方へ頭を向け、仰向いたりうつ伏せたりしていた。眼も口も腫れつぶれ、四肢もむくむだけむくんで、醜い大きなゴム人形のようであった。私は涙をふり落しながら、その人々の形を心に書きとめた。
「お姉さんはよくごらんになれるわね。私は立ちどまって死骸を見たりはできませんわ。」
妹は私をとがめる様子であった。私は答えた。
「人間の眼と作家の眼とふたつの眼で見ているの。」
「書けますか、こんなこと。」
「いつかは書かなくてはならないね。これを見た作家の責任だもの。」(96頁)
「電車道へ出た」ところ。正面に逓信病院(現・広島はくしま病院)。いたるところに「醜い大きなゴム人形のよう」な「死体がころがっていた」。

死体は累々としていた。どの人も病院の方に向っていた。病院の門のあったあたり、そして門の内へ二、三歩入ったところなどに、あがくように手をさしのべて死んでいた。病院へ向かって蹌踉(そうろう)とやって来ては、医者の手に縋(すが)りつくまえに生命をうしなってしまった人々の惨めな姿を見ると、そこに無念の塊が陽炎のように燃え立っていることを感じないではいられなかった。(96-97頁)
現在の正面入口。

当時から残るこの棟は被爆建物として保存されており、「被爆資料室」として公開されている。


横川
河原での三日間の野宿生活のあと、洋子たち親子は避難のため横川駅へと向かった。
三篠橋
橋の上まで歩いて来て、そこから、ぺったりとうつ伏せに倒れ込んでいる広島城を眺めたとき、私の心は波のように大きく動いた。
(中略)広島という起伏のない平面的な街は、白い城があったため立体的になり、古典の味いをのこしていたのだった。広島にも歴史はあったと思い、歴史の屍を踏んで行く嘆きが心をきしませる。(131-132頁)橋は大きな空間にのっぺりと虹のようにかかっていた。いつも左手に見えていた寺町の、あの偉観であった何百軒の寺々もかき消えていた。(132頁)
洋子たちが渡った三篠橋から横川方面を望む。

洋子は「ぺったりとうつ伏せに倒れ込んでいる広島城」を見た。現在はビルが立ち並び、城は見えない。

戦後、鉄筋で建て替えられた現在の広島城。木造で再建する計画が検討されている。

三篠神社
横川を出はずれた三篠(みささ)町の三篠神社は、肌の焼け焦げた巨樹の胴だけを空につきあげて、神社も母屋もあらゆる建物を焼きつくされていた。(134頁)
横川駅の北にある三篠神社。

横川駅
横川駅の手前には海軍病院の救護所が出来ていて、負傷者の群がその天幕を埋めていたが、丁度その前、瓦礫の山の上に、男や女や、老人やそして子供や赤ん坊の死体が、猫の死体ででもあるようにかためて積んであった。(中略)かっと光る真夏の太陽に照らし出された死体の丘には、裸の四肢を醜くひらいて空を睨むように死んでいた太った若い女もあった。どの死体も腫れ太って、金仏の肌のように真黒に焼けている。(134頁)
横川駅。

廿日市駅・玖島
洋子たちは横川から汽車に乗り、廿日市に移動する。
廿日市駅
汽車は平生と変りなく四十分くらいで廿日市に着いた。見覚えのある駅前の広場、春でも夏でも冬でも、どんなに短い休暇にも学校から田舎へ帰ったころ、忘れないで眺めた広場の桜の木の下まで出て来たとき、私は気を失いかけた。妹に土の上へねせて貰った。(137頁)
現在は明るくモダンな建物になっている廿日市駅。

お化けのような火傷の男が電車から降りて来た。頭から全身、手の指先まで繃帯した両腕を前に曲げ、血と膿のしみ出た顔の繃帯の中からまつ毛の焼けた光る眼を出して、きろきろあたりを見た。二人の子供を連れた女の人が駈けよって云いかけた。
「たったいま古田の兄さんが広島の方へ行く電車に乗ったんですよ。」(142頁)
洋子は、このあとの夫婦の涙ながらの会話を鮮明に記している。押し問答の末、男の人が「古田の兄さん」を探しに広島に戻ることになったという。
廿日市駅のホーム。

玖島
玖島は廿日市駅から北東方向に位置する山深い地だ。廿日市峠を越える道は、現在でもかなりの勾配である。
洋子たちは玖島に向かうバスの中で、一人の少年と出会う。少し長いが、引用したい。
車が山の中へ入り、夕ぐれも近づいて来たとき、私はひどくなにか食べたくなった。乾パンを出して噛んだ、ついでに後に可哀そうな少年が掛けている様子だったので、ふり向いて乾パンを少し渡してやった。十ばかりの男の子は頭に血のはみ出たきたない布を巻いていた。少年ははきはきした声で、同じ席の隣りの人に訊かれて、こんな話をしていた。自分はあの朝の空襲で両親と姉を失った。
三人は下敷になって、手や足の先だけ木や土の下から覗かせていたので、自分は交る交る引っぱっていたが、眼の前まで焼けて来て、母の姿は見えないが、声だけきこえ、早く逃げよと云ったので逃げ出した。一人ぼっちになったので、津田の祖母のところへ行こうと思う。津田行へ乗り損ったのでこの車へ乗ったけれど、この先のあたりでよそを廻った津田行が来るそうだから、それに乗りかえなくてはならない。一人で行く決心をした時は涙が出たが、今は哀しくなくなった。
「ええ按配に津田行と出会えばよいがのう。」
隣りの男の人がそういうと、少年はきっぱり答えた。
「会えなかったら歩いて行く。」
(中略)少年は自分で運転台へ出かけて行って、なにか訊いていたが、津田行の通る村の角へ来ると、人をふり向きもせず、だまりこくってひょいと飛び降りた。そして古い茶店の前に佇んで、私どものバスの出るのを、むっつり見送った。
陽が落ちた。空気はさわやかだった。土の匂いや、木々の緑の幹の渋いような香がただよって来たりした。(148-149頁)
玖島分かれ。右折すると玖島、直進すると津田方面。家族を失った少年も、この道を行ったのだろう。

玖島に着いた洋子たちは、数日後に終戦のしらせを聞く。
誰もいないので、涙がこぼれて仕方がなかった。一方では、やれやれと思い、長い戦争だったと思い、安心感が心底を横切った。誰かに会えば、知らぬ人にでも戦争が終ったのはほんとうかどうか、訊かなくてはならないと思った。
(中略)その夜はちっとも眠られなかった。眠らないどころか寝床の上にじっと動かないでいると耐えがたくなり、蚊帳の外に出て坐ったり、くるくる歩いたり、窓から暗い村の方々を眺めたりした。
(中略)母も妹も眠らなかった。妹は何年間か大切にしまっていた背負袋の蠟燭をとり出して灯をつけ、机の端に立ててじっと見詰めていた。そうやっている妹の傷は臭かった。赤ん坊だけがくりくりした可愛い姿で眠っている。赤ん坊の足指のかすり傷と、頬の小さい打撲あとの青いあざとが蚊帳の外から見えた。(156-157頁)
いまものどかな風景が広がる玖島地区。

番外編
大田洋子の墓
洋子は、昭和38年、取材先の福島県で病死。玖島を流れる吉末川のほとりに眠っている。

墓の前を流れる吉末川の清流、奥に地元の名峰・大峰山。

後篇のまとめ
今回はご紹介できませんでしたが、この作品の凄いところは、単なる情景の描写に終わらず、人々の心理や当時の日本を覆っていた社会的な病理にまで考察を深めていることです。
きれいごとではない、生々しい鋭い文章に、こんな作家がいたのかと驚きました。
前篇でも書いたように、この作品、そして大田洋子という作家は、もっと評価されてしかるべきです。
私も、他の作品も読んでいきたいと思っているところです。




